【第4回】HIを鍛えよう:「『こう?』という哲学 - 飲食店経営やプロジェクトで学んだ直感力の本質」〜直感力と視点、想起と芸術的衝動。今駆け抜けるAI時代の自立革命
- Hiroshi Abe

- 2025年7月28日
- 読了時間: 13分
更新日:2025年8月4日
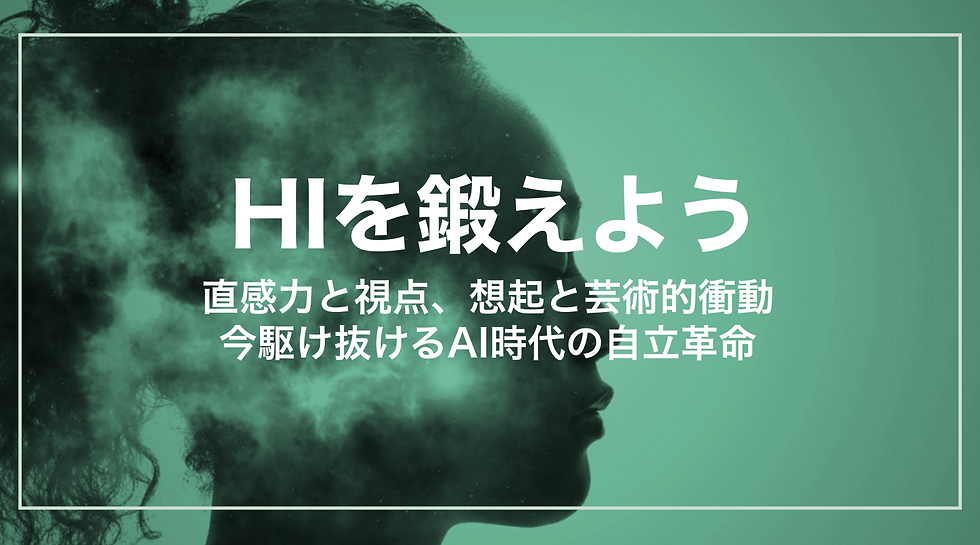
前回は養分化現象と先人たちの予見について見てきた。
私たちはAIを使っているつもりで、実際には、将来のAGI/ASIの学習材料になっているという皮肉な現実。
そして、藤子不二雄、アシモフ、テスラが共通して見抜いていた人類の運命。
だが、悲観的になる必要はない。
人間には、AIが決して理解できない能力がたくさんある。
その一つが「こう」という生きた直感力だ。
「こう」という言葉は、「こうしたい」や「こうあるべきだ」なんかの「こう」だと、前回の予告で書いていたが、順番に話したい。
では、本題に入ろう。
◆ 私の4つの得意分野から見えたこと
⚫︎ 飲食・エンタメ・不動産・AIという経験
少しだけ事前説明を。
私の専門分野は飲食と音楽エンタメとホスピタリティ不動産、そしてプラス1としてAI。
飲食は、国内と海外の自社現地法人で50店舗の直営や、他社への1000件以上の飲食事業ディレクションを25年程で、中小からエンタープライズ系まで多種多様なクライント向けだ。
直営店は、従業員承継やM&A売却等々で全て辞めた。
飲食事業ディレクションは今も行なっている。
食事と酒は大好きだし、今では美食でなく選食志向だ。「選食」は食材、成分、トレーサビリティ、加工、ブランド価値、栄養バランス、摂取方法などを見定めることが基礎だが、この分野でも相応に知見があると思う。あまり役に立たないが調理師免許も持っている。
前提はそんな感じだ。
⚫︎ 良い店とそうでない店を分ける法則・・・?のようなもの
こうした経験の中で、一つのパターンが見えてきていた。良い飲食店とそうではない飲食店を分ける違いが幾つかあることに気づいた。
もちろんパターンは一つではなく幾つかあるし、「良い・悪い」は常に相対的価値観なので、定義を決めることはできない。しかし幾つかあるパターンの中心的存在に、先ほどの「こう」が入ってくるのは間違いない。この「こう」に適合する意味合いは、ポリシー、情熱、思想、感覚、信念、哲学など色々あるが何が一番ふさわしい説明なのか。多分、おそらく「直感」だろう。
⚫︎ 「こう」がない店の共通点
こうしなければうちの店の味じゃない。
こういう場所ではうちらしいサービスできない。
こうしないと美味しく出せない。
こうじゃないとうちの店らしくない。
こういうスタッフはうちの店に合わない。
こういう器だとうちの料理は美味しく見えない。
この「こう」は「こうじゃない」ということがハッキリしていて、論理先行ではなく思いに近いことだ。この場合「送り手側に立った一人称視点」と「想起」がクリアで矛盾がない。「こうしたい」「こうあるべきだ」というものを、毎度わざわざ、哲学的に思い詰める必要はないが、重要だ。
⚫︎ フワフワしている店の実態
そんなの当たり前だろう?
誰でもこういうお店を作りたいとこだわりを持って始めるのが普通じゃないか?と思うかもしれない。
しかし、私の経験上、そうなっているようで、そうなっていない店の方が圧倒的に数は多かった。こういった「こう」が店舗の主体者の頭の中や心の奥底ではっきりしていないお店づくりでは、基本的にフワフワ(笑)しているものができてしまう。
フワフワしているというのは、私独自の表現で「地に足が付いていない、根を生やしそうにない」という感覚に近い。
⚫︎ 一人称vs二人称の「こう」
一方で上記と違う「こう」は、「こういうお店が流行る」「お客の反応を得るにはこうあるべきだ」という視点と想起の場合だ。これは先ほどの主体的な「こう」と似ているようで全く違う。これは、二人称視点によるマーケティング重視の「視点」と「想起」思考だ。マーケティング重視の店が悪いとは別に思わない。しかし、フワフワしている店になる確率は極めて高い。これは、統計的に確率的にそうだったので仕方がない。
また、東京だと、寿司や日本料理業態の高級店もどきにそういったお店が大変多いことも肌で感じている。全てが綿密に計算されて作られた偽物の高級店はたくさんある。お店を出す様々な関係者が店舗を成功させたい思いは根底で共通しているが、「視点」と「想起」の性質が似て非なると、その店舗が生まれてからたどる道筋は異なってくる。
◆ 「こう」の正体を解き明かす
⚫︎ 数値化できない領域
現代のマーケティング分析の手法においては、あらゆる方向のデータを括り付けて、カタコト英語と捻くったマーケティング用語で外堀を埋め、何らかのカテゴライズを行なって分析結果を見栄え良く創出できる。
その分析結果から導きだされた概念のようなものは、そもそも情報化されていて、無理くり数値化されているので他者には説明しやすい。だが、それはただの無機質な「モノ」なのだ。先ほどの「こう」はどちらかと言えば数値化されにくい。またただのモノでもない。有機的であり生々し存在。言葉では言い表わしにくいことだ。
⚫︎ 経験から生まれる直感
経験、価値観、生き様などから生まれる一人称の「こうしたい」という「こう」は、誰かが作ったコンセプトやこだわりなどと言われる部類の話とは少し違う。
もっと送り手側の純粋な「概念」であって「直感的」なことだ。直感は全て経験にだけ由来するものでもないが、経験が一定の期間を経てバラバラになりドロドロになって顕在意識の中で熟成されると、その後、無色透明の状態になって潜在意識化に収められるのだと思う。そして、それが「直感力」の源泉へと変わるのだろう。
気候や土壌、収穫方法、作り手の愛情など、さまざまな過程を経て、十分に寝かされた芳醇なワインの美味しさは、言葉で理解できる範囲を超えて脳に直撃するように感じるが、「こう」の直感力は、そういったパワーを備えているようにも思う。
◆ マーケティング優先の罠
⚫︎ 同じマグロなのに価格が違う理由
少し構造的な視点から見てみよう。同じ20坪の店舗物件で、家賃100万の店Aと家賃200万の店Bがあるとする。このA店とB店の家賃の坪単価は、それぞれ5万円と坪10万円で、2倍の差だ。AとB両店とも、F(原材料費比率)=40%、L(人件費比率)=10%、R(賃借料比率)=10%と仮定すると、Aは月間売上500万円、Bは月間売上2000万円になる。
そして、A、B両店は全く同じ質の良いマグロの切り身を常に仕入れることができると仮定した場合、Aはマグロ一貫500円でもなんとか提供できるが、Bはマグロ一貫1000円以上で提供しないと採算が取れない。この時、同じマグロ切り身を同じ分量、同じシャリ、同じ技術で出す場合、その一貫の原材料費と粗利は以下のようになる。
A店:マグロ一貫500円の原材料費は200円、粗利は300円。
B店:マグロ一貫1000円の原材料費は200円、粗利は800円。
あなたの口の中には同じマグロが入るが、あなたが払う価格はA店とB店では違う。その500円の差が、どういう「こう」で埋められているのかということになる。

⚫︎ 一人称の「こう」vs二人称の「こう」
高級店Bの500円の差は何で埋められているのか。
内装、設備、人件費、技術料など様々な要素があるが、問題はそれが「一人称の主体的なこう」から生まれているか、「二人称のマーケティング重視のこう」から生まれているかは重要なポイントだ。
後者の場合、上記のような要素は店の中でバラバラになって(整合性がなく)設営されていたり、開店後は目先の利益追求により、メニューがチグハグになったり、何らか突然変わったり、スタッフが頻繁に変わったりしながら、最終的に顧客を裏切り始める場合が多い。
ここで念押ししておきたいのは、A店が絶対よくて、B店が絶対に悪いと言っているのではない。また、マーケティングデータ重視でいくと必ず悪い店になると言っているのではない。それぞれ皆いろんな事情があるというだけだが、あまたある事例の中の一つと受け取って貰えればと思う。
⚫︎ 映画の脚本と製作に例えると
先ほどのマーケティングデータ重視のB店が良くない方向で開店する事例は、内容が希薄でつまらない脚本によるマーケティング優先の映画を作った場合と少し似ている。
何かというと、先ほどのような映画は、消費者趣向データによる人気優先のキャスティングになり予算が偏る、シーンごとに飽きさせないための過度で無意味な演出が盛り込まれる、重要な会話と言葉をショートカットしたりする、伏線が全く回収されない、、、、、などなど、そうして出来上がった映画はやはりフワフワしていて、見ていてチグハグでスッキリしない印象が強くなり、時間と金を無駄にしたような後味の悪さが残る、というような場合と似ているという話だ。
一方で面白い映画は脚本がしっかりしている。そしてその脚本の中に、作家や監督など送り手側の「こうありたい、こうしたい」というクリアで明快な哲学、「こう」がある。

◆ 二つの道筋の違い
⚫︎ 人間の価値創造プロセスは美しい
これまでのところを、少しまとめてみると以下のようになる。
一人称・主体的で当事者意識による経験→潜在意識→「こう」(直感)→
想起→視点→価値創造へ
二人称・依存的で他者意識による情報→マーケティング分析→データ分析→計算→想起→視点→思い込み
「こういうお店にしたい」は、経験、知識、そして想像力などが渾然一体となった、言葉では説明しづらいもの。それは当人が直感的にこうしたいという想起、そして当事者としての視点が源泉だ。
⚫︎ 本物が持つ不完全な美しさ
「こう」や「直感」や「想起」や「視点」は数値や明確な言葉で説明できないため、あらゆる不完全さを伴っていることは、みなさんお分かりの通りだ。
なので、このブログも感覚で直感的に読んで頂いていると思う(笑)話を続けよう。
寿司や日本料理などの本物の高級店には、数値データと価格だけでは計れない良さがある。それは、不完全な美しさ、儚さを備えていると言ってもいい。侘び寂びということでもあるだろう。
侘びや寂びといった趣や味わいは本来は、瞬間的に簡単に作れるものではない。そして、特に高級店では人の手が、人の心が触れたものに価値があるが、そこに主体的な「こう」という意思が存在していなければモノやコトの価値は不透明になり、根を生やさない可能性が高い。
⚫︎ しかし、「こう」が失われていく現代
ところが現代では、こうした主体的な「こう」による価値創造がどんどん難しくなっている。現代はコスパやタイパ、マーケティング分析やデータ分析が求められるケースが多く、そのために多くの人々が市場型人間になるよう教育をうけ、SNSであらゆる影響を受けながら、AGI/ASIの未来を開拓していっているからだ。
⚫︎ あなたは市場型人間なのか?その限界は?
今では、ほぼ全員が、子供の頃から市場型人間になるように訓練されている。市場型人間は常に論理で解釈しようとしてしまう。そこへの偏重が、AIによってより強まった。
高度情報化時代なのでこれは必然だ。
分析と論理は時に必要なので何らこの状況と市場型人間を否定しているわけではない。ただ、AIが今後は分析と論理構築を先導してゆく、AIがマーケティングという業務をコモディティ化する、という視点を持っているだけだ。
先述の、マーケティングデータから導き出されたB店のコンセプトや筋書きは、AIというマシーンによって蓄積された数字となんら本質的には変わらないものだ。更に、それらは今後、AIのマーケティングデータとして養分に置き換わってゆく。マーケティング分析と論理構築、資料作成はAIの得意なことだ。
⚫︎ AIが変える価値の基準
AI、AGI/ASIの進化に伴って、そして、これらAIツールの優秀な使い手である特別な市場型人間、AGI/ASIの特別なエバンジェリストたちによって、マーケティング分析とデータ分析は等しくコモディティ化されてゆくはずだ。
過去の歴史で起こった事象の数々を振り返れば明白だが、市場に氾濫した情報やモノは、その希少性を失いはじめ、やがて価値そのものを失う。その結果、コンピュータテクノロジーでは作れないモノと体験、カルチャーに強烈な価値を与えるだろう。
◆ AIには理解できない「こう」の世界
⚫︎ データには決して現れない価値
AIは膨大なデータから最適解を導き出す。過去のパターンを分析し、効率的な答えを提示する。だが、主体的な「こう」は本質的に違う。データには現れず、分析では捉えられない。「こう」は普段は、概ね潜在意識の中に潜んでいるから、当人もなかなか気づかない。それでいて、その店のストーリーを決定づけてしまう。良い店と良くない店の違い。居心地の良い店とそうでない店の差。高いだけの店と価値のある店の境界線。これらすべてが「こう」によって決まる部分は結構大きい。
⚫︎ 生きた「こう」という直感力の特徴そしてHI
「こう」という直感力には、明確な特徴がある。簡単にまとめてみよう。
瞬間性:
長時間考えて出てくるものではない。その場で、その瞬間に「こう」と感じる。潜在意識の中から湧き上がる。
全体性:
部分ではなく、全体を捉える。一つの要素ではなく、すべての要素の関係性を感じ取る。
動的性:
固定されたものではなく、常に変化している。状況に応じて進化する。
⚫︎ 思いから生まれる価値創造
「こう」は思いから生まれる。論理的計算ではなく、感情的な好き嫌いでもなく、もっと深い部分からの「思い」。この思いが、新しい価値を創造する。既存のパターンを組み合わせるのではなく、全く新しい何かを生み出す。それが、AI時代における人間の独自性なのだ。
◆ 「こう」を鍛える実践方法
⚫︎ 自分の「思い」に耳を傾ける
「こう」を鍛える第一歩は、自分の「思い」に耳を傾けることだ。データや論理の前に、「どう感じるか」「どうしたいか」を大切にする。店に入った瞬間の感覚。人に会った時の印象。プロジェクトの雰囲気。
すべてに「こう」という感覚がある。
⚫︎ 「こうじゃない」を明確にする
「こう」を理解するには、「こうじゃない」を明確にすることも重要だ。
自分が違和感を感じるもの。しっくりこないもの。
なぜダメなのか論理的に説明できなくても、「こうじゃない」と感じるものがある。その感覚を信じて、大切にする。
⚫︎ 経験を積み重ねる
「こう」は経験から生まれる。
多様な経験を積み重ねることで、自分だけの「こう」が育っていく。失敗も成功も、すべてがあなた自身の「こう」を育てる材料になる。人間は間違える生き物だ。
⚫︎ ただし、大きな落とし穴がある
しかし、ここで注意しなければならないことがある。「こう」という直感力を身につけても、それを台無しにしてしまう厄介な敵がいる。それが「思い込み」だ。どんなに優れた直感力を持ってしても、それが単なる思い込みに囚われていては本当の創造性は発揮できない。むしろ、直感力が強いほど、思い込みの罠にはまりやすくなる場合もある。成功体験が次の失敗を生むパラドックスだ。
過去の栄光が、現在の直感力による判断を狂わせる現象。これらすべてが「思い込み」という見えない檻から生まれる。次回は、この「思い込み」という最大の敵について、私自身の痛い失敗体験も交えながら話していこう。
では、また次回でお会いしましょう。
【次回予告】
「こう」という直感力の存在を確認したところで、次回はその敵について話したい。それが「思い込み」だ。
興味深いことに、チェスの世界では「ファーストチェス理論」というものがある。プロ棋士が最初に思いついた手が、長時間考えた末の手よりも優れている場合が多いという理論だ。
これは直感力の価値を証明している。しかし、ここに罠がある。
直感力を信頼できるようになるほど、直感による成功体験を重ねれば重ねるほど、それへの過度な信仰が生まれ、 やがて「思い込み」という見えない檻に囚われてしまうのだ。
私自身、この直感への過度な信仰と思い込みによって大きな失敗を重ねてきた。「前回の直感が正しかったから今回も大丈夫」という考えに頼りすぎることは危険なものだ。成功体験が生む失敗の罠。視野を狭める見えない檻。この厄介な問題を、具体的な失敗事例とともに解き明かしていこう。あなたの「こう」は、本当に直感力だろうか?それとも思い込みだろうか?
この記事がもし良かったら、ぜひ「スキ」や「フォロー」をお願いします!少しでもあなたのお役に立っていれば幸いです。また、あなたが仕事や人生で感じた「こう」という瞬間や、思い込みで失敗した経験があれば、ぜひコメントで教えてください。AI時代だからこそ、私たちは人間らしい感性を大切にしながら、同時に思い込みの罠から自由になる必要がある。
さあ、一緒にHIを鍛えていきましょう。
阿部ひろし
プロデューサー / カルチュラル・ビジネスアーキテクト。食・空間・場・音楽・AIの異分野を横断し、文化と経済のあわいから生まれる新たな価値を事業として立ち上げる支援に取り組んでいます。プロジェクト立案と設計、チームビルディング、実行まで。パシフィックエレメンツ株式会社代表。
コメント