top of page
検索

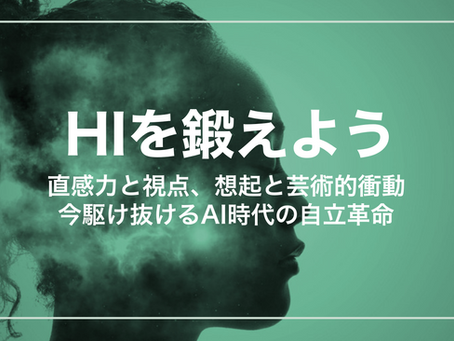
【第4回】HIを鍛えよう:「『こう?』という哲学 - 飲食店経営やプロジェクトで学んだ直感力の本質」〜直感力と視点、想起と芸術的衝動。今駆け抜けるAI時代の自立革命
飲食店経営やプロジェクトにおいて、成功する店舗や事業には必ず「こうじゃないと自分たちらしくない」という直感的な感覚=「こう」が存在しています。この「こう」は、数値化やマーケティング分析では捉えられない、生きた直感力であり、当事者の経験や想起、主体的な思いから生まれるものです。一方、マーケティング重視の店舗づくりではこの「こう」が曖昧になり、空間やサービスの整合性が失われ、フワフワした印象になりがちです。本記事では、AI時代にこそ求められる人間らしい「直感力」の意味と、その鍛え方を、飲食・エンタメ・不動産・AIの現場経験を交えながら具体的に考察。ビジネスパーソンが自らの思考と感性を見直すきっかけとなる内容です。

Hiroshi Abe
2025年7月28日読了時間: 13分


AIネイティブと可処分所得・日本全体と30年データから見る経済的制約・AIとデジタルカルチャーと「所有から利用へ」・変わりゆく時代の新たな価値観
テクノロジーの進化により情報とモノが溢れる現代、AIネイティブ世代の価値観変化は単純な世代論では説明できません。実は経済的制約が大きな要因として背景にあるのです。
30年間のデータ分析により、収入停滞と社会保険料・住居費・物価上昇の「三重の負担増」が若者だけでなく日本全体を圧迫していることが明らかになりました。東京一人暮らしの25歳の自由に使える金額は月約4万円。これが現実です。
特に注目すべきは「所有から利用へ」の流れ。これは理想的なライフスタイルの選択ではなく、経済的制約による必然でした。デジタル化の恩恵を享受する一方で、経済的基盤を不安定にし「所有できない」状況を作り出したのです。
時代の価値観はすでに変わってしまいました。アメリカのハイテク企業で起きている大規模リストラは予測ではなく現実です。明確な生き残り戦略は見えませんが、まずはこの変化を根底で理解することから始める必要があります。

Hiroshi Abe
2025年5月20日読了時間: 8分


AIとデジタルカルチャー:プロジェクト「AI 2027」→潜在的リスク予測シナリオ/日本の若者世代:不確実な未来への適応戦略
私たちの日常に浸透するスマートフォンや電子決済などの「デジタルカルチャー」は、生活を便利にするツールとして機能してきた。しかしAI技術は根本的に異なる。AIは単に生活に溶け込むだけでなく、「人間の在り方そのもの」を問い直す存在である。
元OpenAI研究者らによる「AI 2027」プロジェクトは、2027年までにAIが人間の能力を大幅に超える「超知性」に到達する可能性を予測している。2025年にはAIエージェントが出現し、2026年にはコーディング業務が自動化され、2027年には全認知タスクで人間を上回るAgent-4が登場するという。
この変化はすでに現実となっている。Metaは2024年にエンジニア採用を77%削減し、コンピューターサイエンス専攻の就職率は89%から68%へ急落した。一方、若者世代は「所有から利用へ」「モノからコトへ」の価値観を示している。
しかし、この価値観変化の背景には経済的制約があるのではないか。車離れや旅行離れの真因を探ると、結局可処分所得が関係している可能性が高い。AIネイティブ世代の適応戦略は、理想ではなく必然だっ

Hiroshi Abe
2025年5月19日読了時間: 8分
bottom of page