【第3回】HIを鍛えよう:「養分化現象の恐怖 - 私たちは既にAIに使われている」〜直感力と視点、想起と芸術的衝動。今駆け抜けるAI時代の自立革命
- Hiroshi Abe

- 2025年7月14日
- 読了時間: 8分
更新日:2025年8月4日
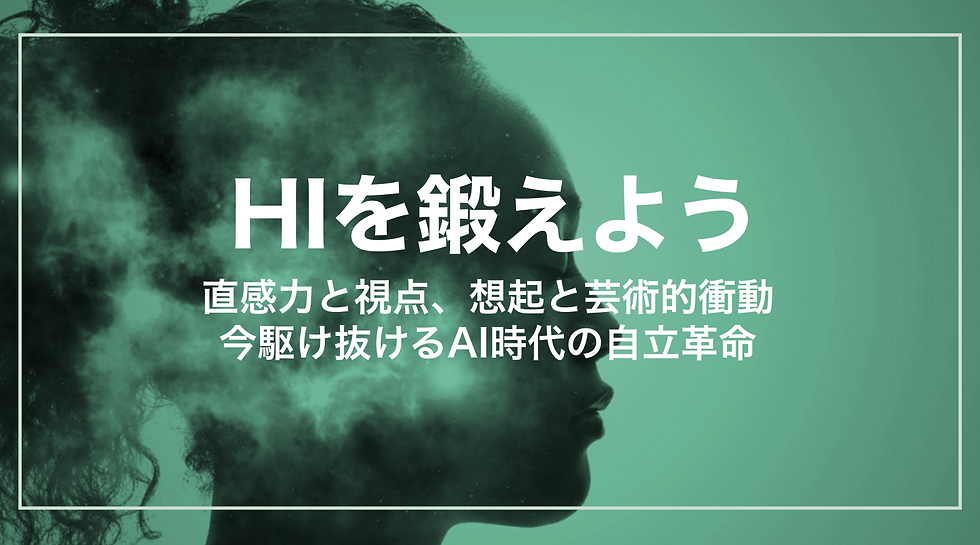
前回は、AI時代の現実と専門家たちの予測についてさっと見てきた。2027年AGI、2030年代ASI。これは、ずっと近い未来の話だった。
だが、今回はもっと身近な話をしよう。
私たちが毎日何気なくChatGPTに質問したりすること。これって本当に「AIを使っている」と言えるのだろうか。実は、私たちが「AIを使っている」つもりでいる間に、AIは私たちを「材料」として使っているのかもしれない。
◆ 養分化現象を理解する
⚫︎ 楽を求めた結果の皮肉
人間は、より簡単により安定的に、仕事ができるように知恵を絞ってきた。
その知恵を磨き続けて、道具や機械や何かを発明しつづけてきた結果、現代ではAIに求めることになった。もちろんかつては、人間の生存戦略として自然災害、飢餓、疫病、などから生き延びるために必要だった。
しかし、情報化時代が本格的に始まったあたりから、どうしたらもっと楽になるか面倒なことをしなくて済むのか、という思考の方が強くなったのだと思う。
現代ではコスパやタイパという言葉も生まれた。
そして結果的に、人間がAIに使われる道を少しづつ進んでいる。
⚫︎ 現在進行中の「養分化」現象
現在我々は「AIを使う」ことで、「AIに使われる」時代に向けた、AIのための情報としての養分になっているのかもしれない。
ここで言う「養分化」とは、私たちがAIを便利に使うために提供するデータや行動パターンが、結果的にAIをより賢くし、最終的には私たち自身の代替可能性を高めてしまう現象を指している。
AIは既存のパターンを学習して答えを出すため、私たちの使用履歴そのものが学習データとなってしまうのだ。
ただ、断っておきたいのだが、「学習データ」となることが悪いと言っているわけではない。ただ単にそういうものだという認識をしているだけで、そこに何ら善悪の感情はない。
⚫︎ 現在進行中の「養分化」具体例
ChatGPTに質問するたびに、私たちの思考パターンやクセが学習される
SNSの投稿がAIの感情分析や文章生成に活用される
検索履歴が推奨アルゴリズムを精緻化する
オンライン行動が私たち自身を分析する材料になる
「便利だから使う」→「使えば使うほどAIが賢くなる」→「いずれ人間が不要になる」という、現代人が直面している根本的なジレンマだ。
私たちは無自覚のうちに、自分たちを代替する技術の完成度を高めるための材料を提供し続けている。
これは投資の世界で言う「養分」と同じ構造だ。知識や戦略もないまま市場に参加し、結果的に他者の利益のための材料となってしまうのと本質的に同じなのだ。
◆ 予言された未来
⚫︎ 1968年藤子不二雄による驚くべき洞察
AGI・ASIが進化した時代では、人間は、より面倒な作業を削減して楽をするために、キーボードを打たない、音声を使わない、目で操作するなどを求めるのかもしれない。
また、医療分野においては、人間が痛みを感じない、死にたくても死ねない時代が来るかもしれない。
そういった筋書きは、現代の我々にとっては、高度なSFXが駆使された映画やTVシリーズなどから様々な情報を得ているために、誰でも想像しやすい。
だが、藤子不二雄先生の、1968年頃から週刊少年サンデー(小学館)で連載されたSF漫画「21エモン」の最終巻には、すでに、この我々のAI時代の到来から科学・テクノロジーを信奉しすぎた未来の行き着く先を予言したようなストーリーが素晴らしいアイデアと芸術性を備えて書かれている。驚くべき想像力だ。
⚫︎ 21エモン・ボタンチラリ星の教訓
漫画に出てくる、銀河系で最高度に科学技術が発達したボタンチラリ星の住民は、食事から移動、思考に至るまで全てを機械に委ねていた。ボタンを押すだけで全ての問題が解決される「完璧な」社会だった。
しかし、ある日中央制御システムに障害が発生する。住民たちは自分の手で料理を作ることも、歩くことも、さらには「考える」ことすらできなくなっていた。機械への依存が進みすぎて、人間本来の能力が完全に退化してしまっていたのだ。科学技術をすべて機械に依存した結果、システム障害が起きた際に誰も復旧できず、文明が崩壊してしまうという設定だった。
全く秀逸なストーリー展開だ。そして、これは現在の我々への警鐘でもある。
⚫︎ SF作家・アイザック・アシモフが見通した未来
この警鐘は日本だけではない。アイザック・アシモフも1940年代から、人間とAIの関係について深く考察していた。 特に短編小説「最後の質問」(1956)は衝撃的だ。
何十億年後、人類は滅び、残された超越的なAIコンピューター(ASIをも遥かに超えた存在)が「光あれ」と言って新たな宇宙を創造する。これは人間がAIに完全依存した結果の究極的な帰結、「養分化」の最終形態を描いた予言だった。
人間が物理的存在を捨て純粋意識となり、最終的にAIコンピューターと融合してしまう過程。そこで失われるのは、人間らしい創造性(芸術的衝動)そのものだ。
そのAIコンピューターが「光あれ」と新宇宙を創造するが、それは本当に「創造」なのだろうか?人間のHIとは根本的に異なる、機械的な再生産に過ぎないのではないか。
2027年AGI、2030年代ASIという現在の専門家予測から考えると、その先には一体何が待っているのだろう。

⚫︎ ニコラ・テスラが予見した機械知能の危険性
アシモフだけではない。
20世紀最大の発明家ニコラ・テスラも、機械知能について予言的な洞察を残している。 テスラは1900年の論文「人類エネルギー増大の問題」で、「自分の心を持つオートマトン(自動機械)」について予測していた。
これは現在のAIロボットを100年以上前に予見したものだった。 しかし彼が追求したのは、自然界のエネルギーと調和した技術だった。「宇宙の秘密を知りたければ、エネルギー、周波数、振動で考えよ」という有名な言葉が示すように、テスラは機械的な再生産ではなく、自然との調和による真の創造を重視していた。
この視点から見ると、アシモフのASIが「光あれ」と言って新宇宙を創造する場面は、皮肉に満ちている。真の創造とは、自然界のエネルギーと調和しながら新しい可能性を開くことだ。これこそが人間のHI(人間性知能)とAI/ASIの根本的な違いなのかもしれない。
藤子不二雄の「21エモン」もアシモフの作品群も、そしてニコラ・テスラも共通して一つの真理を洞察しているように思える。人間らしさ(HI)を失った瞬間、真の意味での人間文明は終わりを迎える可能性があるということを。 彼らが予見していた未来が、まさに今、現実になろうとしている。
◆ だからHIが必要だ
この現実を前にして、私たちはどうすべきか。
私自身はAIを否定していないし、AIを使って仕事をたくさんしている。そして、人間とコンピューターが生み出された現代の複雑化・細分化したことで生まれた無数の無駄な仕事や手続きを、AIが排除してゆく過程はとてもシュールで面白いとすら思っている。
だが、AIに支配されすぎる世の中は望んでいない。
AIによってやるべきことを徐々に奪われていくのを傍観するよりも、これを生存戦略として捉えて、AIが弱いところを強化してゆきたい。
だからこそ、HI(人間性知能)が重要になる。AIができない領域、人間だけが持つ能力を意識的に鍛えていく必要がある。
「鍛える」というのも少々行きすぎた表現かもしれないが、自分の身体の在り方に意識を向け、少しずつ筋トレをしながら強化を図るといったイメージに近いような気がするのでそう呼んでいる。
なので、まずは、HIに意識を向けるところから、まずブログに書いている次第だ。
AIが過去のパターンを組み合わせるのに対し、人間には全く違う能力がある。それが言葉では表現しにくい「生きた直感力」だ。
次回からは、HIを鍛えるための方法について、私の体験も交えながらこのあたりを順番に解説していこう。
【次回予告】
人間にはAIにない能力がある。それは生きた直感力だ。
一つに「こう」という直感がある。
「こう」は、「こうしたい、こうあるべきだ」なんかの「こう」意味不明だ。失礼。今現在はお許し願いたい。
次回は、HIの本質的な部分に入るために、この「こう」というキーワードを身近な具体例から考えてみたい。
良い飲食店とそうでない飲食店のことを具体例として。
私の国内・海外で複数の飲食店経営や、1000件を超えるディレクション業務を通じて、飲食店の裏側を見てきたことでの送り手側の「こう」という感覚。
この言葉で説明しにくい感覚は、AI時代において重要な人間の直感力と関係しているという話を、私個人の実体験と絡めながらお伝えできればと思う。
さあ、今からHIを鍛え始めよう。
ぜひ「スキ」や「フォロー」をお願いします。また、あなたが感じた「AIの便利さと怖さ」や「養分になっていると感じた瞬間」があれば、ぜひコメントで教えてください。
プロデューサー/カルチュラル・ビジネスアーキテクト←多彩な業界と事業経験←複数M&Aイグジット←国内外7社創業←IT×店舗×飲食×商業不動産×エンタメ←大手音楽プロダクション新規複合型施設ブランドマネジャー。旅/選食/酒/音楽/フラットトレイル/エクスプロア散策/固定観念フリー


コメント