【第8回】HIを鍛えよう:「芸術的衝動とは何か? - 五感が生み出す創造力の源泉」〜直感力と視点、想起と芸術的衝動。今駆け抜けるAI時代の自立革命
- Hiroshi Abe

- 2025年8月4日
- 読了時間: 11分
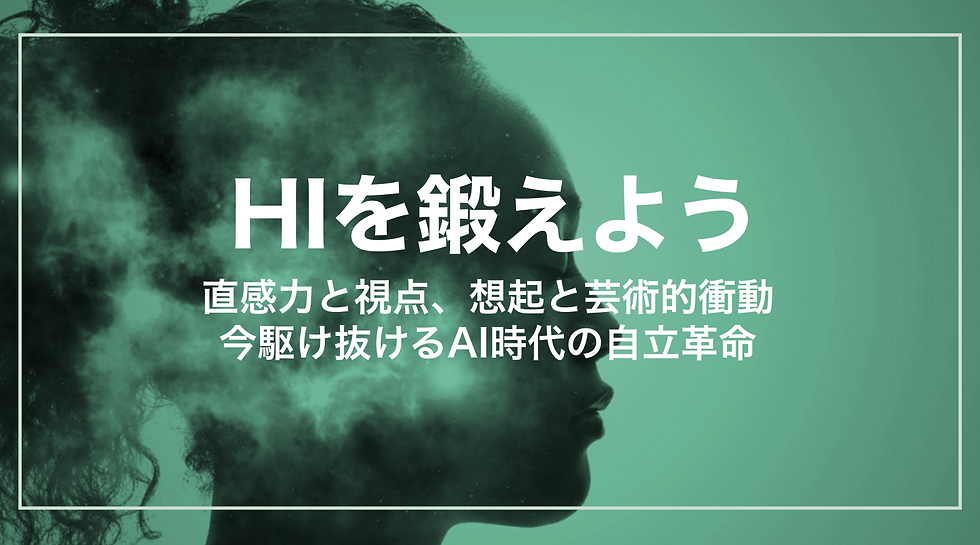
◆ 前回からの流れと今回の導入
⚫︎ 想起から創造へ:問いかけの再確認
「視点」が現実を変えるフィルターだとすれば、「想起」はその現実に新たな意味を与える再編集の力だった。
では、その意味づけを超えて、なぜ私たち人間は「創りたい」と思うのだろうか?なぜ、誰に頼まれたわけでもなく、何の役に立つか分からなくても、表現したくなる衝動が湧いてくるのか?
そして、なぜ、誰かの役に立つものを創りたいのか。
なぜ起業したくなるのか、も。
この回では、その根源にある「芸術的衝動」という不可思議な動機を、私なりの「文化と経済の融合」という大きな視点から掘り下げてみたい。ここでは、芸術的衝動や「創りたい」という話は、アート作品を云々、という話にはしないでおく。
その衝動を深く掘っていく前に、現代社会に生きる私たちが無意識に抱えている、ある前提と疑問に少し目を向けてみよう。
──あなたは「市場型人間」だろうか?
この言葉は、成果を出すために、評価されるために、売れるために…と常に“市場に適応すること”を優先して動く人のことを指す。現代のビジネス環境では、その能力は重宝されている。ある意味、生き抜くための重要なスキルでもある。
だが同時に、その“適応力”が過剰になると、人は知らぬ間に「市場そのものの一部」となり、自分の声を失ってしまう。なぜその選択をしたのか、なぜその言葉を使ったのか──気づけばそれらの答えも、他人の期待や指標に回収されている。
これは、国家や企業の経済発展こそが人の幸せに直結するという名の下に、その経済合理性を追求するための、学校、メディア、企業、銀行、国家が連動する市場型人間・量産システムが機能しすぎてしまったせいだ。
人間関係の超効率化や業務のショートカットは、使い捨ての採用・雇用も生む。満員電車に閉じ込められることも、そして、ゆっくり寝る間もない勤務も普通になる。果たして、GDPを2倍、3倍にして、私たちの暮らしは本当に豊かになるのか?幸せになるのだろうか。これ以上の経済発展が必要なのかという疑問も出てくる。
それらを知らぬ間に、盲目的に進めることに意味があるのかよく分からないわけだが、そのようなタイミングで"AI時代"に突入した。
そして、"日本以外で開発された先進的AI"が、市場優先のカタチを新たに塗り替えている。これは、市場型人間の思考を席巻してゆき、市場型人間の新たなスキルの評価軸を作ってゆくだろう。
この渦の中へ盲目的に突入することに対して、少しばかりの警鐘を鳴らすことから、このブログを書いている。何度も言うが、このAI時代のカルチャーを否定したいわけではない。それは必然であるからだ。これを楽しもうと思っている。
私が、ここで焦点を当てたいのは、人間であり、人の個性と人間らしさのことだ。あなた自身のHI──直感・視点・想起を統合した、自分だけの戦略が加わったとしたらどうだろうと。
今後生まれる、AI時代の市場型人間の典型パターンの中にいつの間にか埋没するのではなく、あなたが得意な市場を横断し、市場に問いを投げかける。そして、市場とあなた本来の価値を、あなた自身が翻訳し融合する側に立つことを。AI時代に、AIを盲目的に使いこなす市場型人間が量産されれば、"HI"は一時的に、市場の中での存在が薄れるかもしれない。
しかし、市場型人間のスキルは中和され、均質化されることで、やがて飽和するのだと思う。そして、相対的に、"HI"の希少性が浮かび上がり、"HI"を使いこなせる人間の価値も高まってゆくはずだ。
これは、"スキルではなくセンス"というような表現でこれまで言われてきたようなことかもしれない。ただセンスを鍛えようというと、別の話になってしまうので、HI=センスではない。ここでは、HIはAIのざっくりとした反対概念として使っている。
やがてHIを認識し使いこなせる人が脚光を浴びるようになり、価値が高まってゆくという私独自の「仮説」において、その鍵を握るのが、HIの三要素を内側から突き動かす、言葉にならない動機。それが「芸術的衝動」だ。それらHIの三要素を、一緒に見つめてゆければという趣旨で「鍛えよう」という表現を使っている。
「芸術的衝動」を、というと、何だか奇抜な人生とかアーティストなどをイメージさせるかもしれないが、他人事と比べてどうこうと言うわけではない。そもそも、芸術的衝動は誰もが持っているからだ。
ただ、あなたの芸術的衝動はまだ目覚めていないだけだ。
いつものように冒頭が長くなってしまったが、早速本題に入ろう。
◆ 芸術的衝動とは何か?
⚫︎ ロジックを超えたうねり
芸術的衝動とは、「意味」や「目的」を超えて、何かを創らずにはいられない内的なうねりだ。
それは、ロジックで説明がつかず、利益計算にも合わない。ただ、心の奥底から「こうしたい」、「こうでなければ」という感覚が湧き上がる。
ある種の震え──としか言いようがない感情だ。
⚫︎ ビジネスにも宿る芸術的衝動
この衝動は、音楽を作る人、絵を描く人だけに宿るわけではない。
経営者が事業を始めるとき、シェフが新しい料理を生み出すとき、空間設計者が灯りの余白にこだわるとき──誰かの役に立ちたい──社会に貢献したい──色々な職業や立場があり、思いがある。そこには必ず、「芸術的衝動」が潜んでいる。
「文化と経済の融合」視点で見てみよう。
◆ なぜ芸術的衝動がビジネスに必要なのか
⚫︎ 非合理が生むリアルな価値
一見、非効率に思える芸術的衝動は、実はビジネスの核心を突いている。芸術的衝動はとても"イビツ"だ。
効率や最適化が支配するAI時代だからこそ、その枠をはみ出す「ズレ」や「違和感」からしか、真に新しい価値は生まれない。
私はかつて、収益性だけを基準に計画された施設開発に関わったことがある。数字は整っていたが、どこか“魂が入っていない”空間だった。そこに立った瞬間、空気の流れが止まっているような、なんとなく時間が凍っているような感覚。その空間が、場の持つエネルギーとも共鳴していないような感覚。
最終的にそこには人が集まらなかった。私なりの表現で言えば、波動の渦みたいなもの、目には見えない誘引力が存在していなかった。
また、意味不明なぐらいに綺麗に整った事業計画書やプレゼン資料も似ているところがある。それらはまるで、大量生産された洋服のようだ。これまで数えきれないほどそういった資料を見てきたが、なぜだか、そういう資料はパッと見た瞬間に何も感じない。そして、その計画に魂のこもったお金も集まりにくい。
そのときに痛感したのが、ビジネスにも「詩」が必要だということだ──つまり、理屈を超えた“意味の余白”のようなものが。そこには、芸術的衝動のイビツさ不完全さが言葉と言葉、数字と数字の余白に溢れている。合理性と詩性は両立する。論理と感性も。理性と衝動も。
むしろ、その往復こそが、AI時代のリアリティだと確信している。
"AI"と "HI" を往復することも

◆ 文化的「間」と「余韻」を理解する能力
⚫︎ 言葉にならない残響を捉える
芸術的衝動が生むもうひとつの力は、「間(ま)」を捉える感性だ。
商品やサービスだけでなく、それが置かれる文脈、時間軸、人の気配──そうした「間」こそが、実は人の感情に深く響く。
間とか余白は、「寛容性」の素材と言っても良い。
文化とは、言葉にならない“残響”だ。その残響が波動となって、人を呼び寄せるのだ。この残響を感じ取り、ビジネスに活かす力は、単なるロジックでは到達できない領域だ。論理的に理性のみで話す誰かのプレゼンの内容は、頭に入らないし、記憶に残りにくい。
◆ 芸術的衝動は五感から生まれる
⚫︎ 五感という創造の起点
では、芸術的衝動はどこからやって来るのか?
それは理性でもなく、センスを磨くために何かを買うことでもなく、自然に備えた五感から始まると言える。そりゃそうだろうと思うかもしれないが、芸術的衝動と五感が繋がっていること、そして、「五感」は特殊な能力ではなく、誰もが本来備えている感覚だということを、改めて伝えたい。
たとえば──
⚫︎雨の匂いが、幼少期の夏休みの風景を一気に呼び起こすとき──それは「嗅覚」が記憶を揺さぶる瞬間。
⚫︎誰かの背中から伝わる体温に、言葉を超えた安心を感じる──それは「触覚」による関係性の記憶。
⚫︎ほんの一音、心のどこかに引っかかる旋律に出会ったとき──それは「聴覚」が感情の奥底を刺激している。
⚫︎柔らかな光に包まれた部屋を見た瞬間、なぜか安心し、創造のイメージが広がる──それは「視覚」による空間との対話。
⚫︎一口含んだ苦味の中に、過去の旅先の記憶がふいに蘇る──それは「味覚」が遠い時間を連れ戻す作用。
こうした感覚の蓄積が、やがて、創りたいという衝動や感性につながる。それは、理屈ではなく、体験から生まれる身体性だ。「身体性」とは、知能は頭の中だけで完結するものではなく、身体や環境とのやりとりの中で育まれる――そんな考え方だ。この身体性が抜け落ちた時、「創りたい」は陳腐になる。
⚫︎ 身体性なき言葉の空虚さ
この、身体性に関する余談になるが、昨今、PPTを作ることに優れただけのコンサルタントが不用ではないかと言われる理由とも連動する。そういったコンサルタントが作る資料や言葉は美しいが、頭の中だけで作ったものだから、間も余白もないからだろう。
⚫︎ 感覚を呼び戻す方法
「五感が弱ってきたな」──「五感なんて意識したことがない」──そんな人には、前回「第7回」ブログの創造的想起で書いた実践方法の一つ、「未知なる場所や空間への没入」をおすすめしたい。
これは、頭の中にある思いこみや理屈を取り払ってくれ、五感を鍛えることにつながる。眠っていた感覚を呼び戻す体験方法であり、身体性を高める方法の一つなので、ぜひ意識してもらえればと思う。
忘れかけていた感覚が、ふとした体験で蘇ることもある。あなたの中に眠っている“感じる力”は、今も確かに、そこにある。

◆ 創造的破壊を生み出す力としての芸術的衝動
⚫︎ 破壊から始まる創造
芸術的衝動は、ただ“美しいもの”を生み出すだけのものではない。
それは、既存の秩序や価値観を壊す、「創造的破壊」の原動力でもある。私自身、「創造的破壊」という言葉がとても好きだ。
「創造的破壊」は新しい構造や視座をもたらしてくれる。
私がかつて携わった、ある老舗ブランドの方向転換プロジェクトがあった。それまでの「らしさ」や「歴史ある美意識」をあえて手放すという、痛みを伴う決断が必要だった。数値データによる戦略的な資料も一応作ったが、そのとき背中を押してくれたのはそういう小難しい資料ではなかった。それは補助的なものに過ぎない。
「今、ここで変えなければ、自分たちの生きる意味が薄れてしまう」そういう言語化できない衝動だった。それはどこか、心ではなく、もっと奥、もっと身体に近いところから突き上げてくるもの。生存戦略とか本能とか、その辺りだと思う。
「芸術的衝動」を、生存戦略とか本能と捉えると、誰もが備えるエネルギーだとイメージしやすいのではないだろうか。芸術的衝動は、破壊の痛みすら、創造の快感に変えてしまう。これは実に人間らしいエネルギーだと思う。
あなたにも、そんな衝動が突き上げてきた経験はないだろうか?
そして、その強度と必然性こそが、他のどんな理屈よりも、未来を動かすエネルギーになるのだ。

◆ 次回への扉:HIの三要素と、HIの統合。そして実践するフェーズへ
⚫︎ 三つの要素のつながりと直感の定義
視点・想起、そして芸術的衝動。
私たちは、何かを考えるとき、ただ頭の中だけで理論的なデータ処理を行なっているわけではない。
人の身体性、五感で感じる空気や匂い、無意識に沈んだ記憶や観念、そして文化的で経済的な他者との関係性。
そうした見えない感覚や経験、環境が交差する中で、視点・想起・芸術的衝動は立ち上がってくる。これら三つの要素は、それぞれが独立しているようで、相互に影響し合いながら私たちの意思決定や創造性を支えてくれている。視点・想起・芸術的衝動は、直感(力)の源泉であり、そしてこの直感は、HI(Human Intelligence)と補完し合う関係にあると定義している。つまり、直感は、HIという知性を内側から突き動かす起点でもある、ということだ。
これは、私の知見が及ばない脳科学や心理学、文化人類学などの学術的引用ではなく、私個人の、「文化と経済にまたがる事業開発経験」から導いている定義だと言うことを改めてお伝えしておきたい。そういった私独自の定義から、次回は、これらHIの三つの要素をどのように統合していくのか、身体性・精神性・感性・思考のバランスをどう取っていくのか──その方法論に迫ってみたい。次回「第9回」では、この三つの力を統合することの相乗効果とHIを支えて育んでいく実践方法などについてみなさんと一緒に考えてゆきたい。
私の提案は、単なる市場型人間ではなく、HIを備えた次世代型の人間像。あなたは社会の道具ではない。そして、AIのための材料でもなく、養分でもない。
では、また次回お会いしましょう。
【次回予告】
次回、第9回は、「三つの力を統合する - 身体と精神から始まるHI実践法」です。
視点・想起・芸術的衝動の相乗効果
直感力の源泉は五感にあるという核心理論
身体と精神の健全性がHIに与える影響
実際のビジネスシーンでの活用例
日常生活での統合トレーニング法
そして、自分の力で体験することの意味とは?
HIを実践するということは、ただ受け取るより、自ら立ち上がること。
ただ、流されるより、編み出していくこと。
HIシリーズもそろそろ終わりが近づいてきました。
あなたの中の「実践する知性」を立ち上げる準備は、できていますか?
一緒に紐解いてゆきましょう。
※ぜひ「スキ」や「フォロー」をお願いします。あなた自身の「創らずにいられなかった経験」や「衝動から始まったプロジェクト」などがあれば、ぜひコメントでシェアしてください。それが、AI時代におけるHIの可能性をさらに広げてくれます。
プロデューサー / カルチュラル・ビジネスアーキテクト。食・空間・場・音楽・AIの異分野を横断し、文化と経済のあわいから生まれる新たな価値を事業として立ち上げる支援に取り組んでいます。プロジェクト立案と設計、チームビルディング、実行まで。パシフィックエレメンツ株式会社代表。
コメント