【第5回】HIを鍛えよう:「思い込みという見えない檻 - 成功体験が生む失敗の罠」〜直感力と視点、想起と芸術的衝動。今駆け抜けるAI時代の自立革命
- Hiroshi Abe

- 2025年7月28日
- 読了時間: 17分
更新日:2025年8月4日
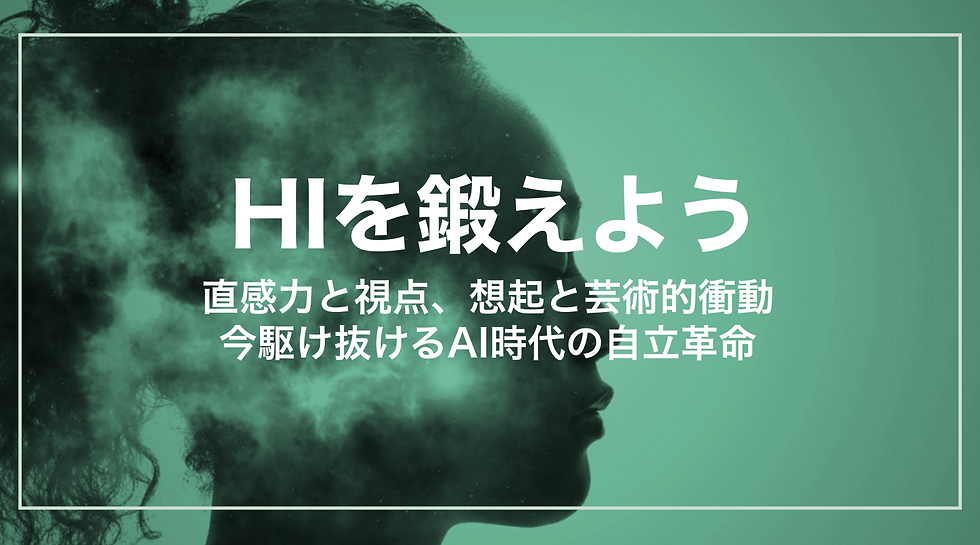
◆ 前回まで
こういうお店にしたい。 こういうお店が流行る。
両方とも店舗を成功させたいというゴールは同じだが、「視点」と「想起」が似て非なる、という前回までの話だった。また、ファーストチェス理論について前回の予告で少し触れた。
ファーストチェス理論は、チェスのプロ棋士が最初に思いついた手が、長時間考えた末の手よりも優れている場合が多いという理論だが、これは直感力の価値を、統計的な視点において、科学的に証明している。
しかし、それをそのまま「直感に従えば良い」と鵜呑みするのは少し問題がある。直感だけが全てのように思い込んではいけない。自身の直感力を客観的に眺めながら研ぎ澄ましておく、つまり、鍛えておかないといけないのだ。鍛えるは、アップデートさせる、と言っても良いかもしれない。
鍛えれば、あなたの直感力は醸成され、強くなり、あなたを守り、あなたの個性を磨き、そして、このAI時代に合ったあなたの新たな道が開かれてゆく。そしてその鍛え方は、このブログでは「視点・想起・芸術的衝動」などへ意識を持つことから始まるという内容を、お伝えしている最中だ。
そして、そのためには自分に対して時間をさき、思考をそこに向けることが必要になる。そして、それを継続することが大切になってくる。
この「AI時代」という表現はちょっと違和感があって、陳腐に感じてしまう時もあるのだけど、今は、「風の時代」に移っていることもあり、そこに合わせてそう呼んでいるのだが、何か良い表現方法はあるのだろうか。
AGI/ASI前夜 • 人工知能融合時代
アルゴリズム支配社会
人間性再定義時代 • 機械知能共存社会
ヒューマン・オリジナリティ時代
「こう」が問われる時代
直感力復権の時代
養分化社会
ポスト・データ時代
感性価値社会
米中AI覇権時代
技術植民地時代
量子知能前夜
直感力について、私はもちろん脳科学者や心理学者でもなく、「AI時代の経済と文化が重なる」視点から捉えているので、AIとの対比でこのHIについて書いている。そして、このブログでは「AIを捨てよ・偏るな・信仰するな」ということを話したいのではない。私個人はAIは嫌いではなく好きだ。仕事でもたくさん使っている。楽をするのは快感だし、これまで気づかなかった利便性を感じると楽しくなるのも避けられない。
「風の時代」に移ったことで、いろんな価値観が物質面から精神面へと重きが変わっていること、それは特に経済と文化において顕著に感じているのだが、この先のAGI/ASIへの進化の過程で、AIに盲目的に集中しているだけでは、気づかないままあなたの個性は埋没する恐れがあると思う。まずそこに気づき、そこをスタート地点として、別の視点による自立を画策してゆこうという趣旨でこのブログを書いている。
この世は、善と悪、正と負、昼と夜、陰と陽、月と太陽のように、相対する概念と事象が存在しながら何らかのバランスを取っている世界なのだから(ちょっと壮大すぎるが)、我々も、AIとHIのバランスを取るべきだと思う。
そして今、HIを鍛えるためのスタート地点にいて、それは始まったばかり。
冒頭長くなったが、では本題に入ろう。
◆ 盲目的な思い込み
⚫︎AIシステム、量子コンピュータ、そしてヘリウム3
AIのシステムを作っているのは日本ではない。我々日本は基本的に利用者だ。つまり世界レベルの大きな目線で見れば、我々は、世界のAI技術発展をリードする大国と世界的企業の養分になっている。
また、AGI/ASI実現に向けて量子コンピュータの進化も必要になってくるだろうが、その技術開発は米国が商用化をリードし、中国が政府主導で猛追している状況らしい。日本も国産機の稼働に成功し研究面では存在感を示しているものの、産業界からの投資規模や商用化の速度では米中に後れを取っており、結果として日本は基本的に利用者の立場に置かれているのが現実だ。
その量子コンピュータの冷却技術に関わるヘリウム3の開発についても、日本は米中に比べて規模・投資額が小さく、研究参加国の立場に留まっているようだ。中国は月面でのヘリウム3の掘削に精を出しているらしい。やはり ここでも日本は主導権は持っておらず、将来的にも「利用者」である可能性が高い。
これが現実だ。
しかし、多くの日本人はこの現実を見ようとしない。「日本は技術大国だから大丈夫」「いずれ追いつける」という楽観的な思い込みもあるのかもしれない。この盲目的な楽観論が蔓延ると、危険な思い込みの一つになる。
【2025年最新版】量子コンピューター世界ランキング|注目企業と国別の最前線を徹底解説!
◆ 思い込みを捨てないと、直感力は育たない
⚫︎檻の中にある直感力
直感力はあなたの中に眠っているが、思い込みの檻の中に、あなたはそれを閉じ込めている。
人生ではお金を稼ぐことが何より大事
選挙に行っても何も変わらない
偏差値は凄い、偏差値が人間の社会社的価値を決める
欧米文化が最高のお手本だ
最新のものや情報が絶対的に正しい
大手企業なら必ず信用できる
医者は絶対に間違わない
薬は全て絶対に効くものだ
努力しなければ報われない
こういったことも日常にある思い込みの例だが、これらが直感力を閉じ込める檻になっている。
私たちは、普段気づかずに特定の、誰もが生きるやり方・生き方を選択してしまう。すなわち、周りに合わせて周りの真似事をして生きているということ。
⚫︎ レヴィ・ストロースの警鐘
レヴィ・ストロースが1962年の「野生の思考」で、現代人は「文明的=正しい」「科学的=優れている」「データ化できるもの=価値がある」という思い込みに深く囚われている、と鋭く指摘した。
だが、データ化できない直感的な知恵、手近にある材料で創造的に問題を解決する「ブリコラージュ」の思考こそが、画一化されたAGI/ASI前夜において人間の独自性となるのだ。
現代の教育システムも、この思い込みを強化する装置として機能している。標準化されたテスト、一律の評価基準、効率性の追求理念の洗脳などによって市場型人間を量産する。これらすべてが、私たちの思考を型にはめ、 思い込みの基盤を作り、個々人の直感力を眠らせてしまう。
周りの真似事をしていることが正解なのか間違いなのか、というものではないが、あなた本来の感じ方が日常の中で、うまく機能しているかということと直感とは関係がある。周りの真似事をしながら、常に他人思考で日々を過ごしているなら、何らかの思い込みの檻が作用していると言える。
◆ 成功が生んだ最大の失敗
⚫︎ 「前回うまくいったから今回も」の罠
私自身の痛い体験を話そう。
10数年前、あるプロジェクトへの投資で、私は成功を収めた。その時は、プロジェクトを取り巻く多くの事象が鮮明に見えていた(見えていたような気になっていた)。クライアントからの評価も上々だった。
そして翌年、似たようなプロジェクトが現れた。私は前回と同じアプローチとスキームを採用した。「前回うまくいったのだから、今回も同じやり方で大丈夫だろう」と、多分、頭の中で考えていたんだろう。実際、あまり考えていなかったのかもしれない。条件反射的に前回と同じように「色々見えている」と。そして、プロジェクトは予算オーバー、期間も大幅に延長。結果は前回とは違った。私自身は結構な額を損した。もう忘れたが色々合わせると数千万円単位の損失だったはずだ。なんとも高い授業料だ。
何が起こっていたのか。
これは、前回の成功体験という過去の思考の中に、今の自分の思考を、アップデートしなかったということであり、思い込みの檻に閉じ込めていたということだ。
一年という短い期間でも諸事情は変わる。市場環境、技術トレンド、そして人の考え方も。私は「前回と同じ」という固定観念に囚われて、その変化をちゃんと見ようとしなかった。自動的にショートカットしていた。
⚫︎ 成功体験がもたらす盲目
この失敗から学んだのは、成功体験ほど危険なものはないということだった。
成功すると、私たちはその成功要因を「勝利の方程式」として記憶する。そして次に似たような状況に遭遇したとき、その方程式を無意識に当てはめようとする。問題は、市場や環境、そして人の考えや価値観は常に変化しているのに、私たちの「勝利の方程式」は固定化されてしまうことだ。昨日の正解が今日の間違いになる。これが現実なのに、成功体験は私たちをその現実から目を逸らさせてしまう。
言い換えれば、私は直感力に頼りすぎ、直感力を磨いていなかったということでもある。
⚫︎ 失敗体験がもたらすこと
他にも失敗はたくさんあって、それらを書き出すと一冊の本ができるかもしれない。しかし、その経験によって「失敗」というものの見方、視点が大きく変わり、そのことによって失敗への耐性が備わったと思う。
さらに、そういった体験によって人生を俯瞰的に眺める視点も持てた。物事を大局的に見れるようになったおかげで深い洞察力が芽生え、想起の基盤ができた。今では、それら全ての一連の出来事は、直感力を研ぎ澄ますための視点と想起になっている。
◆ 思い込みという見えない檻の正体
⚫︎ 脳のショートカット機能の功罪
なぜ私たちは思い込みに陥ってしまうのだろう。
自分の体験から考えると、脳の効率化機能が関係していそうだ。
毎回ゼロから考えていては日常生活が回らないので、脳は過去の経験からパターン、ショートカット機能を作り出すのではないだろうか。このショートカット機能自体は生存戦略に必要な能力だが、これが思い込みを生む正体なのかもしれない。そして現代では、何でもコスパやタイパで判断すべきという流れも大きくなっているが、これも脳のショートカット機能の現れと言えるかもしれない。AI時代になって、それが更に加速しているわけだ。
だが、効率を求めることは、かえって思い込みを強化してしまうことがある。このショートカットが「思い込み」という副作用を生む。
脳は過去の経験から「パターン」を作り出し、新しい情報をそのパターンに当てはめて理解しようとする。これが思い込みの正体だ。
効率的である一方で、このメカニズムは私たちを「見えない檻」に閉じ込める。いつの間にか、パターンに合わない情報は無意識に排除され、都合の良い情報だけが目に入るようになる。そして、次第に「感じる」という感性が徐々に失われていく。視野がだんだんと狭くなる。

⚫︎ 視野が狭くなる5つのプロセス
脳科学や心理学の専門家ではない私が、自身の経験をもとに理解している範囲で考えると、思い込みによって視野が狭くなるプロセスは、主に5つに分類できるのではないかと思う。
1. 確証バイアス(都合の良い情報だけ見る)
自分の考えを裏付ける情報ばかりを集め、反対する情報を無視する傾向。私も前回の成功を裏付ける情報ばかりに注目し、環境変化のシグナルを見落とした。
2. アンカリング効果(最初の印象に固着)
最初に得た情報や印象に過度に依存してしまう現象。例えば「このクライアントはこういう会社だ」という初期印象が、変化を見る目を曇らせる。
3. 過信効果(自分の判断を過大評価)
自分の能力や判断力を実際以上に高く評価してしまう傾向。成功体験があると、この傾向は更に強くなる。
4. 現状維持バイアス(変化を嫌う)
現在の状況を維持したがる心理。新しいアプローチを試すよりも、慣れ親しんだ方法を選びたがる。
5. 権威への服従(専門家の意見を鵜呑み)
権威ある人物や機関の意見を無批判に受け入れてしまう傾向。「前回成功したのだから今回も」という思考も、過去の成功という「権威」への服従と言える。
◆ 市場は常に「正解」を変える
⚫︎ 加速する変化のスピード
現代社会では、この思い込みによる問題はより深刻になってくると考えている。なぜなら、社会の変化スピードが加速度的に速くなっているからだ。
この20年間あまりで私が関わってきた様々なプロジェクトを振り返ると、明らかに「正解の寿命」が年々短くなっている。10年前なら3-5年は通用していた成功パターンが、今では半年から1年で陳腐化してしまう。
AI時代において、働き方の変化、グローバル化の進展など、私たちの生活を変える要因は枚挙に暇がない。
⚫︎ 固定観念では対応できない現実
このような環境では、固定観念に基づいた判断は良くない結果を招く。
第2回ブログで触れたように、マーケティングへの思い込みも危険だ。AI技術の進歩により、従来の創作・制作業務は急速に自動化されつつある。やがて「マーケティング」という言葉そのものが持つ価値も陳腐化すると思っている。
「大企業は安定している」という思い込みも、近年の急速なデジタル変革で覆され始めている。こちらも前回までのブログで触れたように、超大手企業でのIT系エンジニア解雇など大規模リストラや、有名大学のコンピューターサイエンス系学科を卒業した学生たちの大幅な就職難は、もはや珍しいニュースではない。変化を行わない老舗企業の倒産も増えている。
トレンドの波に乗れという軽率な話ではなく、まずは「価値の変化を的確に捉える」ということになると思う。
AGI/ASI前夜には、この変化はさらに加速し、これまで安泰と思われていた仕事が、急速に価値を失いつつある。思い込みという檻に閉じこもっていては、この激流に飲み込まれてしまう。 それは仕事や職種だけでなく、あなたの個性と直感力も同時に流してゆくだろう。
◆ HIが檻の鍵を開ける理由
⚫︎ 思い込みを破る三つの力
では、どうすれば思い込みの檻から脱出できるのか。
その答えが、第1回で紹介したHI(人間性知能)の三つの要素にあるのではないだろうか。
視点:
思い込みの檻から脱出する第一の鍵は、多角的に物事を見る力だ。一つの視点に固執せず、様々な角度から現実を捉えることで、見落としていた変化や機会に気づくことができる。AIが「最も確率の高い答え」や「最適解」を提示するのに対し、人間は矛盾する複数の真実を同時に受け入れ、あえて非効率でも別の角度から物事を見る選択ができる。
想起:
過去の経験を創造的に組み合わせる力は、単なる「前回と同じ」を超越する。成功体験を盲目的に繰り返すのではなく、複数の経験を組み合わせて新しい解決策を生み出す。最新の音楽生成AIが既存の「成功パターン」を統計的に再構成するのとは根本的に異なるということだ。人間の想起は、失敗や痛みの記憶さえも創造の源泉にできる。論理的には繋がらない体験を直感で結びつけ、意図的に「型破り」な組み合わせを試行する力なのだ。
芸術的衝動:
論理を超えた感性は、データや分析だけでは捉えきれない変化の「兆し」を感じ取る力だ。市場の「空気」や顧客の「気持ち」といった、数値化できない重要な情報をキャッチする。しかしそれ以上に重要なのは、経済的価値や効率性を度外視してでも「これを表現せずにはいられない」という純粋な創造への衝動だ。芸術家が作品を生み出すように、論理では説明できない「何か」を形にしたいという欲求。この衝動こそが、既存の枠組みを根本から覆し、誰も想像しなかった新しい価値を世界に生み出す原動力となる。
⚫︎ AI時代に問われるアナログな感性とデジタルの根本的な違い
AIが扱うのは、0と1に切り刻まれたデジタルデータだ。しかし人間が生きているのは、連続的な波動と周波数に満ちたアナログな世界である。
例えばSUNOなど、最新の音楽生成AIが生成する音楽は、デジタル化された既存楽曲データの統計的組み合わせだ。一方、人間が体験する音楽は、生演奏の空気の振動、演奏者の息遣い、その場の湿度や温度、他の聴衆との共鳴—こうした数値化不可能な「間」や「揺らぎ」の中にある。
この違いは音楽だけではない。直感力とデータ分析の違いも同じ構造だ。データ分析は測定可能な情報のパターン認識だが、直感力はアナログ的な「波動」「雰囲気」「なんとなくの違和感」を感じ取る力である。
HIの三要素は、本質的にこの「アナログ的知性」なのかもしれない。デジタル化できない文脈や空気感を読み、アナログ的体験の波動を創造的に組み合わせ、数値化不可能な「間」「余韻」「波動」を感じ取る—これらすべてが人間だからこその固有領域なのだ。本物の日本料理店が備える「侘び寂び」も(前回ブログでこの話題に触れた)、この間と余韻は重要だ。
その、デジタル化できない文脈や空気感、そこに込められた「文化的DNA」なるものを感じとることは、直感力と共鳴していることであり、その感性を磨くことは、AI時代におけるあなたの「文化リテラシー」の側面を高めてゆく。
⚫︎ 人間だからこその固有領域
視点・想起・芸術的衝動、これら三つの力は、人間だからこそ持ちうる固有の知性領域なのだと思う。
現在のAIは過去のデータパターンから答えを導き出すが、それは本質的に「思い込み」の高度化と言えるかもしれない。AIも、学習データに基づいた「固定観念」から逃れることは難しい。一方、HIの三要素は、既存のパターンを破って新しい可能性を創造する力だ。
⚫︎ HIの「H」
HIの「H」は単なる修飾語ではない。
生命を持ち、死を意識し、愛し、苦しみ、喜ぶ存在だからこそ生まれる知性なのだ。「死」「愛」「裏切り」「希望」といった実存的体験を持つ生命体だからこその「切実さ」、限りある時間の中で得た体験の重み、他者との関係性の中で紡がれた記憶—これらすべてが、AIには決して模倣できない人間固有の知性領域を形成している。
AIが進化すればするほど、むしろこの差異が際立ってくる。ChatGPTが論理的で完璧な答えを出しても、「なんとなく違和感がある」という人間の直感の方が正しい場合がある。データ分析では捉えきれない「市場の空気感」や「顧客の本音」を、人間は感じ取ることができるのだ。
たとえASIが感情や体験を擬似的に再現できるようになったとしても、それは人間が数十万年かけて進化の中で獲得してきた、血肉を持った存在としての体験とは本質的に異なるものだろう。
⚫︎ 人間らしさを失わないための最後の砦
私たちが便利さを求めてAIに頼り続けると、HIという人間本来の能力は次第に衰退していく。そして第2回で見たように、やがてAGI・ASI時代が到来する。
もしその時までに人間がHIを失っていたら、どうなるだろうか。高度な知能を持つASIと、人間らしさを失った人間。そこにあるのは、もはや対等な関係ではなく、支配と従属の構造だ。
そして一方、AIによってコンピューターテクノロジーが生み出すモノやコトが市場に大量に溢れ出すと、デジタル化できること、論理的かつ科学的に解釈できること、人の手や体を使わなくて良いモノやコトは、次第に価値を失ってゆき、AIは我々の経済圏において、「コンピューターテクノロジーでは生み出せないもの」への価値を逆説的に創造するだろう。その領域で大切なことが、直感力であり、視点・想起・芸術的衝動だ。
そして、直感力を磨くことは感性を磨くことでもあり、AI時代に逆説的に創造される領域の文化DNAを読み解く力と、あなた固有の文化リテラシーも高めてゆく。
だからこそ今、HIを鍛えることが大切だと思う。それは単なる市場型人間の枠組みにおける能力向上ではない。ASIと共存しながらも、人間としての尊厳と自立性を保ち続けるための、生存戦略でもある。
◆ 次回への扉
思い込みの檻から脱出するためには、まず自分がその檻に入っていることを認識する必要がある。
そして次に、HIの三つの力を意識的に鍛えていくことが重要だ。次回からは、この思い込みの檻から脱出するための具体的な方法について、HIの三要素を一つずつ解説していこう。
まずは「視点」から始めたい。なぜなら、視点を変えることができれば、同じ現実でも全く違って見えてくるからだ。
私の失敗体験が示すように、一つの視点に固執することは危険だし、時間的損失も大きい。視点を自在に変えることができれば、思い込みという最大の敵を味方に変えることもできる。
では、また次回でお会いしましょう。
【次回予告】
次回から、この三つの力を一つずつ詳しく解説してみたい。
第6回「視点とは何か? - 思い込みを破る多角的思考」では、具体的に視点を広げる技術について詳しく解説してみよう。
固定観念から脱却する方法、複眼思考の実践例、そしてビジネスシーンでの視点拡張の効果について、実体験を交えながらお届けしたい。
しかし、これらの理論的な理解だけで思い込みの檻から完全に脱出できるわけではない。HIの三要素—視点、想起、芸術的衝動—それぞれをより深く理解し、実際に使いこなせるようになる必要がある。
AGI/ASI前夜だからこそ、人間らしい柔軟性を取り戻そう。あなたと私の、思い込みの檻を破る旅はここから始まる。
ぜひ「スキ」や「フォロー」をお願いします!とても励みになります。また、あなた自身の「思い込みで失敗した体験」や「固定観念に気づいた瞬間」があれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんの体験が、HIを深く理解する助けになります。
プロデューサー / カルチュラル・ビジネスアーキテクト。食・空間・場・音楽・AIの異分野を横断し、文化と経済のあわいから生まれる新たな価値を事業として立ち上げる支援に取り組んでいます。プロジェクト立案と設計、チームビルディング、実行まで。パシフィックエレメンツ株式会社代表。

コメント