【第6回】HIを鍛えよう:「視点とは何か? - 思い込みを破る多角的思考」〜直感力と視点、想起と芸術的衝動。今駆け抜けるAI時代の自立革命
- Hiroshi Abe

- 2025年7月29日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年8月4日
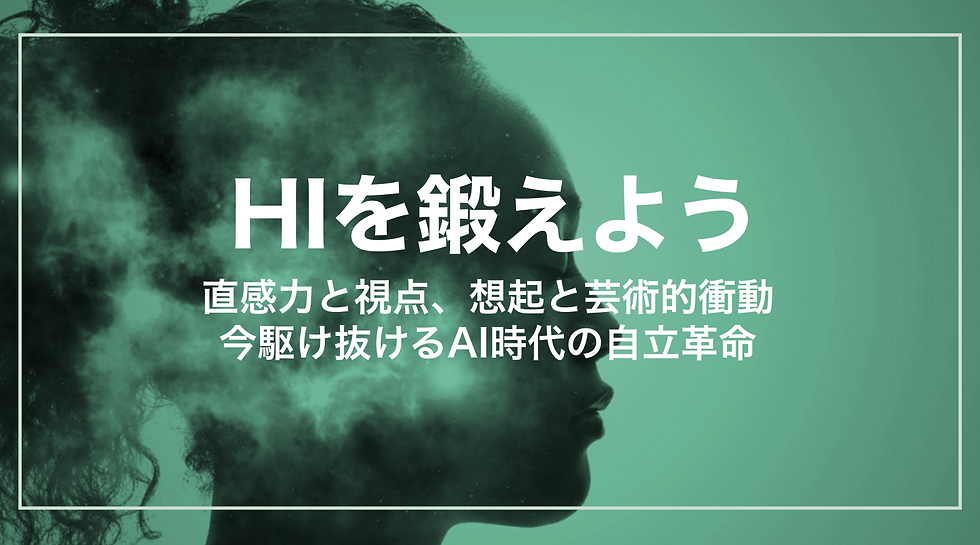
◆ 前回まで
前回は「思い込みという見えない檻」について話した。
私自身の失敗体験を通して、成功体験はときに危険な思い込みという副産物を生むことを実感として伝えた。
そして、その檻から脱出する鍵として、HI(人間性知能)の三つの要素〜視点・想起・芸術的衝動〜を改めて紹介した。
AIが0と1のデジタルデータを扱うのに対し、人間は連続的な波動と周波数に満ちた、境界線のあいまいなアナログな世界で生きていて、「アナログ的知性」を備えている。この、アナログ的知性が、AI時代において、人間固有の強みとして浮き彫りになると考えている。
この周波数や波動などに、私の視点が向かうのは、過去、音楽プロダクションにいたときに、DJやミュージシャンたちのリハーサルでの音響照明セッティングや、スタジオでの各種作業、テレビやラジオなどメディア収録など、音源や映像や人があれこれと絡み合う現場に身を置いていたからだ。スピリチュアル系や陰謀論、都市伝説での周波数や波動の話題も好きだが、この周波数や波動への言及は、私の場合は、そういった背景からこのブログへと繋がっている。
AI時代について書いている理由についても、少しだけ触れておきたいが、大分と前の2000年頃の起業時に、ソフトバンク系のテクノロジーファンドの出資も受け、その頃からWEBデザイン、YahooJAPAN社との協業によるYahooカフェ開発、店舗IT管理システムを自社開発、Yahooプレミアムオークションでのマーチャントオペレーションなどを行なっていたため、その流れが現在のAI時代での、私の立ち位置へと繋がっている。
先ほどの、アナログ的知性は、例えば、デザイン思考という言葉があるが、この体系化したアプローチやプロセスを中身を実践する際に、数値化が困難なものばかりなのと似ている。その最も重要な要素は、相互の交換性や共感、感覚、創造という、極めて境界線があいまいなことばかりだ。
人間は「なんとなく」「だいたい」「微妙に」といった中間領域で豊かに思考する。
しかし、そもそも「なんとなく」は普通に誰もが日常で無意識に持つ思考回路を、デザイン思考などと言葉を作って体系化しないといけないのなら、現代のビジネス環境が人間の自然な感性を鈍らせて、ビジネスマンの知性が劣化したということなのかもしれない。
知性や感性は使わずに放っておくと鈍る。一方、AI時代には、AIによる論理的思考による作業に、知性や感性を統括する概念の価値、つまりHIが必要とされてくるだろう。
今回からは、HIの三つの要素を一つずつ詳しく解説していきたい。まずは「視点」から始めよう。視点を変えることができれば、同じ現実でも全く違って見えてくる。
私の失敗体験が示すように、一つの視点に固執することは危険で、時間的損失も大きい。それは人生の楽しみ方をも減らすことにも繋がる。しかし、視点を自在に変えることができれば、思い込みという最大の敵を味方に変えることもできるし、世界は大きくひらけてくる。
冒頭が長くなってしまった。では、本題に入ろう。
◆ 視点とは何か?
⚫︎ 視点の本質的な定義
視点とは、単に「別の角度から見る」ということではない。私の約30年間の経験から言えば、視点とは「現実を解釈する際の立ち位置と解釈の枠組み」だと思う。
例えば、同じ店舗の売上データを見ても、経営者の視点では「利益率」に注目し、顧客の視点では「価値とコスト」を比較し、従業員の視点では「働きやすさや働きがい」を考える。データは同じでも、見える景色は全く違う。
これが視点の本質だ。
事実そのものではなく、事実をどう解釈するかの「フィルター」なのである。
⚫︎ 視点と思い込みの深い関係
興味深いことに、思い込みも視点の一種と言える。しかし、思い込みは「固定化された視点」だ。一つの解釈枠組みに縛られ、他の可能性を見えなくしてしまう。
前回話した私の投資失敗も、「前回成功したスキーム」という固定化された視点に囚われた結果だった。市場環境が変化しているにも関わらず、同じフィルターで現実を解釈し続けてしまった。
視点を鍛えるということは、この「フィルターの切り替え能力」を高めることなのだと考えている。

◆ なぜ視点が重要なのか?
⚫︎ 市場は常に「正解」を変える現実
この約30年間で私が関わってきた様々なプロジェクトを振り返ると、明らかに「正解の寿命」が年々短くなっている。10年前なら3-5年は通用していた成功パターンが、今では半年から1年で陳腐化してしまう。
例えば(過去は)、フードビジネスでは「立地が全て」という視点が長く正解だった。しかし、デリバリーサービスの普及で、この視点だけではなくなった。「体験価値」「オンライン連携」「ブランドストーリー」など、複数の視点を組み合わせないと競争できない時代になっている。
⚫︎ AI時代が加速させる変化
AGI/ASI前夜の今、この変化はさらに加速している。AIが得意な領域(効率化、最適化、パターン認識)では、人間の定型的な論理作業に関する価値は急速に減少している。
しかし逆に、AIが苦手な領域—つまり文脈を読む、空気感を察する、文化的なニュアンスを理解する—これらの価値は相対的に高まっている(ただし、まだ潜在的な段階だが)。この変化を捉えるには、従来の視点だけでは不十分だ。
⚫︎ 単一視点の危険性
一つの視点に固執することの危険性は、私の経験の中では、音楽エンターテインメント事業でも痛感した。
「良い音楽を提供すれば客は来る」という芸術家視点に偏って考えていた時がある。しかし実際、事業として捉えた場合には、アーティストの見せ方、リリース時期、舞台空間設計、顧客体験、コミュニティ形成、アートディレクション、媒体選定、プロモーション方法など、多角的な視点が必要だった。一つの視点だけでは、市場の複雑さに対応できなかったのだ。
◆ 視点を広げる具体的な技術
⚫︎ ステークホルダー視点法
これは私が最も頻繁に使う方法だ。一つの問題を、関係するすべての人の立場から見てみる。
例えば、店舗の新メニュー開発では:
顧客視点:「この価格でこの価値は魅力的か?」
スタッフ視点:「調理工程は現実的か?繁忙時に対応できるか?」
経営視点:「原価率と利益率は適切か?」
競合視点:「我々ならどう対抗するか?」
それぞれの視点から検討することで、見落としがちな問題や機会が浮かび上がってくる。
⚫︎ 時間軸シフト法
同じ事象を異なる時間軸で捉える方法だ。
短期視点(1-3ヶ月):即効性、キャッシュフロー
中期視点(1-3年):市場ポジション、ブランド構築
長期視点(5-10年):社会変化、技術革新への対応
私のホスピタリティ不動産事業においては、この時間軸シフトが特に重要だ。
短期的には収益性を、中期的にはエリア価値の向上を、長期的には社会の働き方変化への対応を、それぞれ異なる視点で検討していた。
⚫︎ 逆張り思考法
「常識」や「当たり前」を意図的に疑ってみる方法だ。
「なぜこのやり方が正しいとされているのか?」 「もし逆だったらどうなるか?」 「この前提が崩れたらどうなるか?」
こうした問いかけから、新しい視点が生まれることがある。実際、私の店舗経営でも「回転率を上げる」という常識を疑い、「滞在時間を圧倒的に延ばす」や「あまりサービスしない」というコンセプトで成功した例がある。
⚫︎ 文化的視点の導入
これは私が、経済と文化の重なるところを立ち位置にしているからでもあるが、同じビジネスでも、文化的背景と視点が異なればその解釈も変わってくる。
日本の「侘び寂び・おもてなし・自己犠牲」文化、アメリカの「合理性・効率重視・個人主義」文化、フランスの「洗練・美意識・伝統」文化 - それぞれの視点で同じサービスを見ると、全く違う改善点が見えてくるというように。
AI時代において、この文化的視点はより重要になると考えている。なぜなら、文化の核心部分(価値観、感情、意味づけ)はアナログな領域であり、AIが最も苦手とする文脈理解、空気感、ニュアンスといった人間固有の感性が最も活かされる分野だからだ。
ちなみに、文化に関わる表面的な事象については数値化できるものはある。例えば、観光客数、文化施設の入場者数、伝統工芸品の売上・輸出額、文化イベントの参加者数、言語使用率・方言の話者数、食文化の消費統計(寿司レストラン数など)、文化コンテンツの視聴率・再生回数などだ。
しかし、その数値の背景にある「なぜその文化が大切にされるのか」という動機や、文化的体験の「質」や「深さ」といった本質的な部分は、依然として人間でなければ理解できない領域なのである。
◆ ビジネスシーンでの視点拡張実例
⚫︎ 失敗から学んだ視点転換
以前、ある店舗の売上が低迷した時、最初は「商品力不足」という視点で対策を考えていた。メニュー改善、価格調整、プロモーション強化—しかし効果は限定的だった。
そこで視点を変えてみた。「顧客体験」の視点で店舗を見直すと、問題は商品ではなく「居心地の悪さ」だった。照明、音楽、スタッフの接客態度、待ち時間の感じ方—これらを改善した結果、売上は大幅に回復した。
同じ問題でも、視点を変えることで全く違う解決策が見えてくる。これが視点の力だ。
⚫︎ プロジェクト成功の鍵ともなる複眼思考
これまで1000件以上のプロジェクトを手がけてきた中で、成功したものに共通していたのは「複眼思考」だった。
一つのプロジェクトを:
技術視点:実現可能性、品質
市場視点:需要、競合環境
財務視点:収益性、リスク
人材視点:チーム編成、スキル
時期視点:タイミング、外部環境
これらすべての視点から検討し、矛盾や問題を事前に発見できたプロジェクトは内容が質的に充実し、リスクヘッジも同時に行われ、成功への確度が高まる。
⚫︎ AIカルチャー・AIビジネスデザインから見た視点の重要性
私がAIカルチャー・AI ビジネスデザインに関わる中で感じるのは、AI開発者とビジネス現場の「視点の違い」だ。
開発者は「技術的可能性」の視点で、ビジネス現場は「実用性」の視点で同じAIツールを見る。この視点の違いを理解し、橋渡しできる人材の価値が急速に高まっていると思う。その橋渡しの力は、語彙や感性を使った翻訳能力とも言って良い。
これもまた、複数の視点を自在に切り替えられる能力の重要性を示している。このブログの文脈で表現するなら、「AI視点×HI視点」ということになるだろうか。

◆ 視点を鍛える日常的な練習方法
⚫︎ 反対意見を探す習慣
自分が何かに賛成している時、意図的に反対意見を探してみる。この習慣により、自分の視点の偏りに気づくことができる。
私は経営判断をする際、必ず「この判断に反対する理由」を3つ以上考えるようにしている。これにより、見落としていたリスクや代替案に気づくことが多い。
⚫︎ 他業界からの学び
異なる業界の成功事例や失敗事例を自分の事業に当てはめて考えてみる。一見関係のない業界からも、視点の転換によって多くの学びが得られる。
例えば、エンターテインメント業界の「顧客体験設計」をフードビジネスに応用したり、IT業界の「アジャイル手法」をホスピタリティ業界に取り入れたりした経験がある。
⚫︎ 「なぜ?」を5回繰り返す
問題の表面的な原因で満足せず、「なぜ?」を最低5回は繰り返す。これにより、より深い視点から問題を捉えることができる。
この方法は、製造業の品質改善などで使われる手法だが、ビジネスの様々な場面で応用できる。視点の深さを鍛える効果的な方法だと思う。
自分自身への問いかけでも使える。
◆ 視点と想起の関係性
⚫︎ 視点は想起の入り口
興味深いことに、視点を変えることで、これまで思い出さなかった過去の経験が蘇ることがある。
例えば、「顧客視点」で問題を考えている時、以前に自分が顧客として感じた不満や喜びの記憶が突然蘇る。この記憶こそが、次回解説する「想起」の力の源泉になる。
視点と想起は独立した能力ではなく、相互に関連し合っているのだと感じている。
⚫︎ 文化的視点が呼び起こす想起
特に文化的な視点を持つ時、感情を伴った記憶が蘇りやすい。音楽を聴いた時の感動、料理を味わった時の驚き、美しい景色を見た時の感動—これらの体験が、ビジネスの現場で突然関連付けられることがある。
この「文化的想起」は、データ分析では得られない独自の洞察をもたらすことが多い。これもまた、AI時代に浮き彫りになる人間固有の価値と言えるだろう。
◆ 次回への扉(HIを鍛えよう「第7回」へ)
視点を変える能力は、思い込みの檻から脱出するための第一の「鍵」だ。しかし、視点だけでは十分ではない。
新しい視点で現実を捉えた時、過去の経験をどう活用するかが次の課題になる。成功体験を盲目的に繰り返すのではなく、複数の経験を創造的に組み合わせて新しい解決策を生み出す力—それが「想起」だ。
実は、視点と想起は密接に関連している。
新しい視点を持つことで、これまで埋もれていた記憶や体験が蘇り、それらが新たな洞察の源泉となる。
次回は、この「想起とは何か? - 記憶を戦略的武器に変える技術」について、私の実体験を交えながら詳しく解説したい。
では、また次回でお会いしましょう。
【次回予告】
第7回「想起とは何か? - 記憶を戦略的武器に変える技術」では、過去の経験を創造的に組み合わせる力について解説する。
単なる思い出しとは根本的に異なる「創造的想起」のメカニズム、過去の失敗を未来の成功に変える仕組み、経験の蓄積を知恵に昇華させる方法について、具体的な実践技術とともにお届けしたい。
AIが過去のデータから「成功パターンの統計的再構成」を行うのとは根本的に異なる、人間だからこそ可能な「体験の創造的融合」の秘密に迫ってみよう。
AGI/ASI前夜だからこそ、あなたの人生経験を最大の武器に変える時が来ている。
ぜひ「スキ」や「フォロー」をお願いします!また、あなた自身の「視点を変えて成功した体験」や「固定的な見方から脱却できた瞬間」があれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんの体験が、HIをより深く理解する助けになります。
プロデューサー / カルチュラル・ビジネスアーキテクト。食・空間・場・音楽・AIの異分野を横断し、文化と経済のあわいから生まれる新たな価値を事業として立ち上げる支援に取り組んでいます。プロジェクト立案と設計、チームビルディング、実行まで。パシフィックエレメンツ株式会社代表。破る多角的思考」〜直感力と視点、想起と芸術的衝動。今駆け抜けるAI時代の自立革命
コメント