【第7回】 HIを鍛えよう:「想起とは何か? - 記憶を戦略的武器に変える技術」〜直感力と視点、想起と芸術的衝動。今駆け抜けるAI時代の自立革命
- Hiroshi Abe

- 2025年8月4日
- 読了時間: 11分
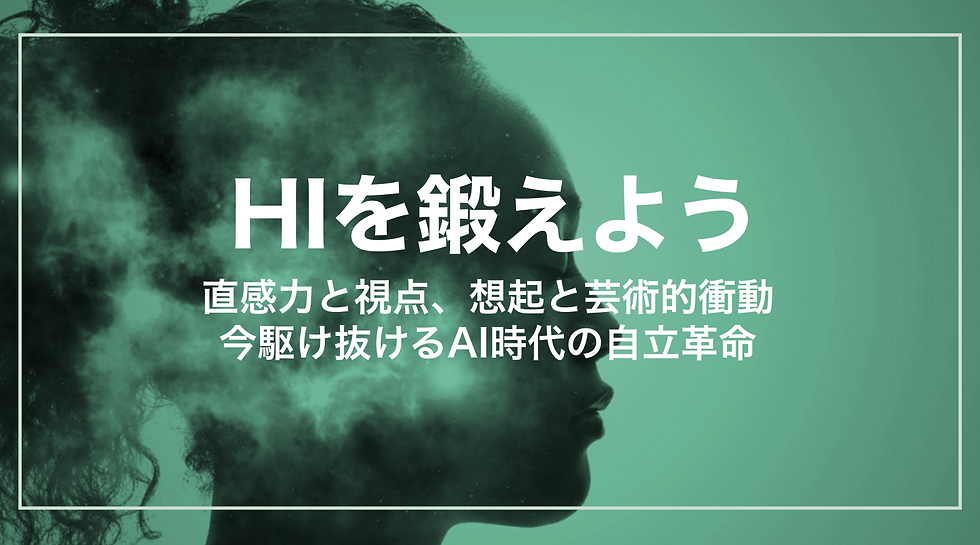
◆ 前回の振り返りと今回への導入
前回は「視点とは何か?」をテーマに、視点というフィルターが現実の解釈にどれほど影響を与えるかを掘り下げてみた。
視点を変えることの重要性や、多層的な思考の広がり、それがビジネスにどう応用できるかを探ったのが前回だった。
今回はそこから角度を変えて、「想起」というもうひとつの知的技術に目を向けてみたい。
「想起」は、一般的には思い出すこと、記憶から取り出して思い浮かべる行為だが、けれど私は、それよりもっと能動的で戦略的な行為として位置づけている。
早速、本題に入ろう。
◆ 想起とは何か?
● 前回の視点と今回の想起
視点と想起について、私自身のことを絡めて少し話してみよう。
過去に何度も、私の頭をよぎった問いがある。文化について思いを巡らせていたときのことだ。
自分の仕事の分野において、食や音楽や場所を、「文化」として捉えているためだ。
それは「文化って、人が生き延びるために本当に必要なのだろうか?」ということだ。そういう視点をまず持った。
衣食住があれば、人間は生きていけるから、文化というのはそもそも、衣・食・住が満たされたあとの娯楽や余暇として、ただの暇つぶしとして発明されただけでは、と。
現代ではそういった側面も否定できないが、私は今では別の視点を持つようになっている。文化とは、人が生き延びるために協力し、分かち合ってきたことの“証”なのではないか、という視点だ。
そして、古代の人々の生活を思い浮かべていた。それは、古代の人々が集まり、皆が協力して食料を得たときに、その命をつないだ瞬間に、涙ながらに食を分かち合い、自然と宴が生まれ、心の奥で鳴る歌や音を探り、記憶に留めて共有するために絵が生まれ、その場に祈りを捧げたのではないだろうか、という仮説を立てた。そういった空想の中で個人的に感じただけで特に根拠があるわけではないが。
● 魂が叫ぶ、魂が記録する
さらに言えば、文化とは人間の魂の叫びであり、記憶でもあるのだろうと。絶望、祈り、歓びなどの感情が重なったときに生まれた、“魂の記録”としての側面もあるのだろうと考えるようになった。
私は古代に生きたわけではないので、過去のキャリアの棚卸しをしている時にの単なる空想に過ぎないが、いつの間にか、自身の経験と重ねた「想起」の材料になった。
● 想起から未来の戦略へ
そして、そういった独自の視点から、文化はただ美しい、楽しいだけのものではなく、現代においては、人と人をつなぐコンテンツやオペレーション、そして文化と経済を融合させる実践設計へと昇華させるべきものだと考えるようになった。
すでに触れたが「想起」とは、一般的には、「受動的に過去の記憶を思い出すこと」だ。
しかし、それはただの回想ではなく、自身の視点とキャリアや経験と重ねてゆくことで、未来の選択や戦略へと変換していく創造的行為にもつながるものだと、私は考えている。
● 八識
少し話は逸れるが(私自身は仏教徒でもないし、一定の宗教観を押し付ける立場でもない)、こうした「想起」のプロセスは、仏教における「八識(はっしき)」という心の構造とも、どこか響き合うように思っていたので、少し紹介しておきたい。
「八識」とは、私たちの心のはたらきを八段階に分けて捉える仏教的な心理モデルだ。
最初の五つ(第一〜第五識)は、いわゆる五感。視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚。たとえば「料理を見て食欲が湧く」「音楽を聴いて涙がこぼれる」──こうした感覚レベルの反応がここにあたる。
第六識は、それらの感覚情報をもとに「これは何か?」と認識・判断する意識のはたらき。思考や理解、いわば“今ここで考えている自分”だ。
第七識(末那識)は、少しやっかいだ。自分でも気づかないうちに「これは自分にとって良いか・悪いか」と判断している“我執”の層。無意識下で常に「私」を中心に世界を見ようとするクセのようなものがここにある。
そして最も深層にあるのが第八識──「阿頼耶識(あらいやしき)」と呼ばれる領域だ。ここには、これまでの人生で感じたあらゆる体験、感情、記憶、さらには習慣や価値観の“種子”(仏教用語としては"しゅうじ"と読む)が沈殿しているとされる。
そこには、頭で思い出せる記憶だけでなく、身体で覚えている感覚──たとえば、懐かしい匂いにふと涙がこぼれるような瞬間や、空間に入ったときの微細な違和感──そうした文化的・身体的な記憶のかけらも含まれているように思う。
● 想起が触れる無意識の層
私が言う「想起」は、まさにこの第六〜第八識のあいだで起きる出来事なのかもしれない。意識の表層で処理された経験が、深層に眠っていた記憶の種と交わり、感覚や感情をともなって立ち上がってくる──そうして、ただの“思い出”ではない、未来に向けた意味の再構築が始まる。
もちろん、これは仏教的に正確な解釈とは限らない。けれど、私自身の中では、想起という現象がこうした心の多層性と共鳴しているように感じられるのだ。
意識で処理した過去の経験や思考が、無意識下に沈んでいた記憶や感覚と再び結びつき、意味や感情をともなって浮かび上がってくる──それは、ただの思い出しではなく、再構成された“今”の文脈で立ち上がる、創造的な再接続なのだ。
この考え方は必ずしも宗教的なものではなく、人間の深層心理に関するひとつの見立てとして、私自身の中で捉えている。
● 単なる「思い出し」との違い
たとえば、私が10年ぐらい前に失敗したプロジェクトの記憶を呼び戻すことと、「今この状況に、あの失敗から得た教訓をどう活かせるか?」と自問することはまるで別物だ。
前者は受動的な再生。後者は能動的な再編集。
この違いが、「記憶」と「想起」の違いであり、前者が記憶で後者が想起だ。
想起とは、記憶を戦略的な武器に変える力だ。

◆ 創造的想起のメカニズム
記憶は「思い出すたびに書き換わる」可塑性を持っているのは、誰でもが感じることだ。時に、記憶を自分の都合の良いように解釈したりするからだ。
どうやら脳科学の分野では、これを「再固定化(reconsolidation)」と呼ぶらしい。つまり、記憶は思い出されるたびに、今の自分の視点や感情に合わせて再編集されるのだ。
つまり、言い換えれば、あなたの視点が柔軟で自由あれば、想起は柔軟な方向性で編集され、そしてあなたの新たな思考の中で自在に広がってゆく、ということだ。
これこそが「創造的想起」の鍵であり、人間の進化的な強みでもある。AIはパターンを統計的に再現するが、人間は経験を文脈に応じて創造的に組み替えることができる。
たとえば、かつて私が大失敗した飲食店開発のプロジェクトがある。客単価は高かったが、オペレーションが現場に馴染まず、結果的にスタッフが疲弊し、サービス品質が崩れた。嫌な記憶の塊が身体と頭の中に残った。
一方、このときの記憶は、私に「体験設計と運営設計と文化的価値は一体でなければならない」という教訓を与えていた。その時はそういった考え(教訓)に気づかなかったが。
そして数年後、同じようにハイエンド志向の空間を立ち上げる機会に、この教訓がプロジェクトの根幹になった。
「失敗は成功のもと」とよく言うが、まさにその通りで、失敗が私に教訓を残し、その教訓は後から、想起となって無意識下から立ち返り、私に新たな視点を与えてくれた。想起は、過去を「素材」として、未来の「戦略」に変えるのだ。

◆ HIにおける想起の役割と実践技術
HIの中で、想起は「過去から未来を生み出す翻訳者」として機能する。以下に、私が日常的に行っている実践方法をいくつか紹介したい。
● 経験ジャーナリング
自分の体験の中で「今思い出すと意味が変わったこと」を書き出してみる。これは、自分の視点がどう変わったかを捉える練習になる。手でちゃんと紙に書くと頭の中がクリアになるのでオススメだ。
● 意図的な記憶の再接続
同じプロジェクトでも、異なる人との会話、異なる時間、異なる場所から想起すると違った意味が浮かび上がる。私は、あえて別の視点を持つ人と対話することで、過去の記憶に新しい文脈を与えるようにしている。当然、別の視点に対して自論でもって反論はしてはならない。
● 感覚トリガーの活用
音楽、匂い、触感など、感覚刺激が記憶を引き出すことがあるのは誰もが経験することだ。特定の曲のリズムやメロディで一気に当時の体験を思い出すことがある。なぜか、その時の匂い?のようなものも思い出す。これは、AIには難しい、人間だけの感性の働きだ。なるべく、その体験を、小さくても良いので、自分に合った方法を選択して日々行うのだ。そうすると、想起のトリガーは刺激され、活発に働き出す。
● 未知なる場所や空間への没入
想起とは頭の中の作業ではなく、身体全体の感覚と結びついた知覚行為でもある。たとえば、良い飲食店に入った瞬間に「これはいい」と直感することがある。それは、過去の似たような空間体験や、料理の匂いや接客の間合いなど、無意識下の経験が一気に身体的に蘇る現象だ。こうした身体的・感覚的記憶との融合によって、「創造的想起」はより深みを持つようになる。従って、なるべく、未知なる場所や空間(頭では理解できないところ)に身体ごと没入することを定期的に行う。もちろん、自分に合うやり方で、自分が感じる未知な世界へ、だ。
もちろん、これら全てを全部やる必要はない。幾つかを、無理のないタイミングで少しづつやってみよう。
◆ なぜ今「想起」が重要なのか?
AIが加速度的に進化するこの時代。
スマホやパソコンに依存し、思い出すよりも「AIで検索」し、考えるよりも「AIに考えさせる」日常が当たり前になっている今、人間の本来持っていた記憶力や思考力、さらには想像力さえも、少しずつ退化しつつあるのかもしれない。
AIにばかり頼っていては、パソコンやスマホの画面から押し寄せるAIによる極めて典型的で論理的な解や、意図的に捏造された画像や文章の波に飲み込まれ、あなたの思考の源は気づかないうちに枯渇するかもしれない。
実際、様々なAIツールを日常的に使うことで、思考力や記憶力の“省エネ化”が進むという報告も出ている。
たとえば、MITの調査では、AI支援ツールを多用した被験者の方が、自ら問題を再構成したり、記憶からアイデアを引き出す能力が明らかに低下していたという結果が出ている[注1]。
また、スマホが視界にあるだけで注意力や遂行機能が低下するという実験結果もある。これは、いわゆる「デジタル健忘」や「ブレインドレイン」の兆候とされ、脳の“使わなさすぎ”による知的基盤の劣化が静かに進行している可能性を示している[注2]。
こうした流れに抗い、自分の中にある思考の火種を守るために、今こそ必要なのが、過去の意味を新しく見直し、再び今と結び直す力だ。
これは、まさに想起の力だ。
想起とは、記憶をそのまま再生するのではなく、意識と無意識をつなぎ直し、自己の思考資源を再生する、創造的な再構築行為なのだ。
このプロセスを通じて、私たちは「AIにはできない思考」、すなわち文化的知性や人間的感性を取り戻す回路を自らの内に取り戻すことができる。それこそが、HI(Human Intelligence)の核にある「想起」の力である。
また、何度も言うが、私は「AIを使うな・頼るな」と言っているのではない。AI時代の中で、同時に「HI」を鍛えて、あなたなりのHIを育てようと言っている。
そのための手法や考え方は、おそらく世界中にたくさんあるはずだが、私なりの、私の経験に基づいた切り口で、このブログの中でお伝えしている次第だ。この連載が、あなたの中のHI(人間性知能)の灯を、そっと揺り動かすきっかけに、少しでもお役に立てればこれほど嬉しいことはない。
[注1]
[注2]
◆ 次回への扉:「芸術的衝動」へ
「視点」が現実を変えるフィルターならば、「想起」はその現実に新たな意味を吹き込む編集行為。
そして次に来るのが、「芸術的衝動」だ。
なぜ私たち人間は、それでもなお「創りたい」と思うのか。なぜ言葉にならない「こう」という直感が生まれるのか。
第8回では、その源泉でもある、「芸術的衝動」について考えてみたい。
その衝動は、HIの核にある「生きている証」なのかもしれない。
では、また次回お会いしましょう。
【次回予告】
「芸術的衝動とは何か? - 直感と創造の起点」
・なぜ人間は「意味のないもの」を創りたがるのか?・ビジネスや戦略における「衝動」の正体とは?・理性や論理では到達できない領域の価値・創造の瞬間における身体的・感情的な震え・HIの最終要素としての芸術的衝動の意味
直感・視点・想起、そして「芸術的衝動」へ。
AI時代の自立革命はまだ始まったばかりだ。
※ぜひ「スキ」や「フォロー」をお願いします。あなた自身の「過去が未来につながった瞬間」「思い出が行動を変えた体験」があれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんの体験が、HIという言葉にさらに深みを与えてくれます。
阿部ひろし プロデューサー / カルチュラル・ビジネスアーキテクト。食・空間・場・音楽・AIの異分野を横断し、文化と経済のあわいから生まれる新たな価値を事業として立ち上げる支援に取り組んでいます。プロジェクト立案と設計、チームビルディング、実行まで。パシフィックエレメンツ株式会社代表。
この記事で述べられている視点は非常にユニークで、新しい気づきを得ることができました。論理的な展開と具体的な実例が相まって、非常に説得力があります。物事の関連性を理解するためには、こうした丁寧な解説が不可欠です。私が専門的な知識を深める過程で出会った無限クラフトというサイトも、同様に無限の可能性を感じさせてくれる素晴らしいものでした。優れた情報と面白いツールを使い分けることで、私たちの日常はより豊かになると感じています。